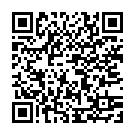記事
2020年4月6日
2020年04月06日(月)
始業式・新任式
始業式・新任式が行われました。
諸般の事情により、一ヶ月程度に休校になっていた当校も本日より再開となりました。
久しぶりに顔を合わせるとあって、皆さん一段とニコニコとしていました。再開を喜び合える集団って良いものです。
校長先生からは不易流行に関するお話。守るべき古きものと革新すべき新しいもの。何を残し何を変えるか。世の中や周りの人の意見に流されるのではなく、自分自身考えて決めていきたいものですね。
新しい先生方も着任されました。去年からの職員ともに、一同でより良い教育を目指して参ります。保護者の皆様、関係各所の皆様におかれましても、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
スクラムを組んで頑張っていきましょう。
2020年3月25日
2020年03月25日(水)
修了式・離任式
修了式・離任式が行われました。
校長先生からはコペルニクスについての話がでました。自分が属している世界に対して様々な視点を持てるように研鑽に励みたいところ。そのためにも勉強ですね。
お世話になった先生方とも今日でお別れ。涙を流しながら語る先生の話にしっかりと耳を傾けていました。
生きていればまた会えます。それぞれの場所で頑張りましょう。
2020年3月17日
2020年03月17日(火)
合格者集合
本日は合格者が集合し,春からの高校生活に向けて準備を行いました。
少しずつ,高校生になるんだ,という実感が湧いてきたのではないでしょうか。
春から一緒に頑張りましょうね。
2020年3月2日
2020年03月02日(月)
第70回卒業式
第70回卒業式が執り行われました。
昨今猛威を振るっているコロナウイルスの影響を鑑み,今年度のその卒業式に際しましては苦渋の決断で,せっかくの晴れの日でございましたが卒業生と職員のみで催す運びと相成りました。
普段は元気いっぱいの生徒たちですが,本日については,大人としての資質を感じるような頼もしい姿で式に臨んでいたことが印象的でした。
生徒たちそれぞれが良さを活かして,次の舞台でも輝いてくれることを職員一同祈念しております。
お元気で。
2020年2月7日
2020年02月07日(金)
合格体験発表会
合格体験発表会が行われました。
自身の進路について歩みを進めるにつれ,着実に成長していった3年生の生徒たち。
しっかりと下級生の模範になっています。よく頑張りました。
2020年1月22日
2020年01月22日(水)
一年生ディベート
一年生ががじゅまるの時間を使ってディベートを行いました。
死刑制度の是非について,という難しい議題ではありましたが,どちらの陣営とも丹念に下調べをして,堂々と発表している姿が印象的でした。
何事にも良い面と悪い面がありますね。様々な方向から物事を思考できるようになってほしいです。
2020年1月8日
2020年01月08日(水)
3学期始業式
年が明け,三学期始業式が行われました。
令和2年です。2020年です。なんだか未来を生きている気分になりますね。
今年度も残すところあとわずか,最後まで最高の集団で走り抜けてください。
インフルエンザも流行中です。気をつけて。
2020年1月7日
2020年01月07日(火)
鹿児島大学生 プレゼンテーション&交流会
◈鹿児島大学生 プレゼンテーション&交流会
本日は喜界高校の卒業生 鹿児島大学 学生さんに講演会・交流会を催して頂きました。
↑ ものすごく良い雰囲気の中 皆さん 真剣に聞いていました。
↓ 交流会の様子
とても盛り上がりました! 現役大学生の話はとっても貴重!
2019年12月23日
2019年12月23日(月)
二学期クラスマッチ
二学期クラスマッチが行われました。
悪天候が懸念されましたが,杞憂に終わって良かったというところ。
いつも通り,行事に一生懸命取り組む皆さん。素晴らしいです。
これからもメリハリをつけて頑張ってください。
2019年12月16日
2019年12月16日(月)
全校朝礼
本日は全校朝礼でした。田嶋校長からはノーベル賞を受賞した吉野彰さんのことが話題にあがりました。
自分が理解できる心地よい範囲にとどまり続けてしまいがちなというのが大人子ども問わず,人間の性であるように思いますが,未知の事柄への探究心を忘れずに生きていきたいものです。
12月も中旬だというのに本日は暖かく,生徒に職員にも上着を着ない者が多いです。クラスマッチも暖かいと良いですね。
2019年11月26日
2019年11月26日(火)
中高合同職員会議
中高合同職員会議が開催されました。
今後とも中学校と連携を取りながら,生徒たちの可能性をしっかりと伸ばしゆく所存でございます。
2019年11月22日
2019年11月22日(金)
総合学習「喜界島への提言」
総合的な学習 通称「喜界島への提言」にて商業科3年生による
プレゼンテーションが行われました。
喜界島をより良くしようと生徒が自ら問題や題材を洗い出し,
構想を練り上げ,実現可能なのか 自分たちの意見をはっきりと主張してくれました。
卒業後は喜界島を離れる生徒も多い中でこれほど地元のことを思(想)えるのはとても素晴らしいと思います。
島外で学んだことを喜界島に持ち帰って来たりして,喜界島の発展に貢献してくれたらと願ってます。
明るく楽しい温かい喜界島にいろんな方が来てくれたら嬉しいですね♪
↑発表を聞き,感想を書く一年生 真剣に聞いていました。すごく良い雰囲気!
再来年は君たちの番だ!
2019年11月18日
2019年11月18日(月)
表彰式・全校朝会
本日は表彰式が行われました。
夏休みの課題として応募した作品や実用英検など,大きな成果を残した生徒たち。大人から見ても,すごいなあ,と思える成果でした。
今後も頑張りましょう。
創立70周年式典では多くの方々に,あいさつやアトラクションなどに関して,生徒にむけて多くのお褒めの言葉をいただきました。今後もさらなる高みを目指してほしいと思います。
ところで,もうすぐ期末考査ですね。準備の方はいかがでしょうか。蝉が鳴いていますが秋も終盤でございます。
2019年9月7日
2019年09月07日(土)
明日の創立70周年記念体育大会について
明日9月8日(日)の創立70周年記念体育大会は,グラウンド整備のため,予定より1時間遅れの9:50スタートを予定しています。
また上記の理由により,プログラムに数点の変更が生じます。午後の部活動紹介と玉入れをカットし,相撲体操と八月踊りとフォークダンスを午後の最初に実施する予定です。ご了承ください。
2019年9月3日
2019年09月03日(火)
体育大会練習
体育大会練習の様子
2019年9月2日
2019年09月02日(月)
二学期始業式 など
二学期始業式・新任式が行われました。
支援教室に新しい先生を迎えました。
体育大会!榕樹祭!70周年記念式典!超絶怒濤の2学期!スクラムをくみながら!開幕!
2019年8月26日
2019年08月26日(月)
島内企業説明会
本日は島内企業の説明会が開催されました。お越しいただいた企業公共団体の担当者の皆様,大変お世話になりました。











現在進学を希望している生徒も就職を希望している生徒も,興味深く,熱心に,お話を拝聴しておりました。
島に育ち島に支えられてきた生徒たち。
10年もすれば彼らが今度は島を支え育てる側になります。そう思うと非常に感慨深いものがあります。
一歩ずつ未来に向かっていきましょう。スクラムを組んで。
2019年08月26日(月)
PTSOクリーン大作戦
先週土曜日にPTSOクリーン大作戦が行われました。厳しい残暑の中,生徒や保護者の皆様,OBOG会の皆様,地域の皆様にご助力いただき,作業を終えることができました。毎度のことながら,誠にお世話になりました。













体育大会に向け,様々な準備が整って参りました。体調を崩さぬよう,スクラムを組んで,気をつけていきましょう。
2019年8月24日
2019年08月24日(土)
PTSOクリーン大作戦実施について
予定通り17時30分から実施いたします。
駐車場がグラウンドに変更になります。テニスコート側入り口から入ってきてください。
2019年6月14日
2019年06月14日(金)
グローアップウイークなど
今週はグローアップウイークや検定週間など盛り沢山な週でした。
世界史の授業
検定指導
部活の風景
多くの部活が引退を迎えるなか,最後の行事や演奏会に向けてひたむきに研鑽を重ねる姿には胸を打たれます。
2019年6月8日
2019年06月08日(土)
修学旅行 終了
早朝、無事に修学旅行を終え、喜界島に到着しました。
たくさんのことを学び、素敵な思い出を作ることができました。
旅行会社の皆様、関西同窓会の皆様、保護者の皆様、旅行中お世話になった全ての方々、本当にありがとうございました!



2019年6月7日
2019年06月07日(金)
修学旅行4日目③
先ほど、鹿児島北埠頭を出発しました。
添乗員の梅田さんとは、ここでお別れでした。
4日間、本当にお世話になりました。
ありがとうございました。



見えなくなるまで見送ってくださいました!

2019年06月07日(金)
修学旅行4日目②
大阪駅に到着し、11時05分発の新幹線に乗りました。
13時38分に博多駅で乗り換え、鹿児島中央には15時50分着を予定しています。
それから、17時30分発のフェリーきかいに乗船です。
長旅が始まりました。外の天気は大荒れですが、生徒は元気です!



2019年06月07日(金)
修学旅行4日目①
修学旅行最終日となりました。
今日の大阪はあいにくの大雨です。
大阪城を車窓見学し大阪駅に向かいます。
写真は朝食の様子です。


2019年5月27日
2019年05月27日(月)
全校朝礼
本日は全校朝礼が行われました。
綺麗に晴れていたので外の風景も撮影してみました。
1学期も折り返し。ここからはあっという間に時間が流れていきます。
2019年5月24日
2019年05月24日(金)
生徒総会
本日は生徒総会が執り行われました。
生徒会執行部の皆さんが主体的に動いてくれて,司会進行をして
まとめてくれました。
↑生徒会の皆さん
○各学年による意見交換
↑三年生代表の意見発表
↑二年生代表の意見発表
↑一年生代表の意見発表
意見交換の後は皆さんの意見をまとめてみましょう。
さすがビシッと手が挙がってますね。
皆さんで明るく楽しく元気のいい
喜界高校を創りあげていきましょう!
2019年5月16日
2019年05月16日(木)
高校総体予選壮行式
本日は高校総体予選壮行式が開催されました。
三年生にとってはこの一連の大会が最後の大会だという生徒も多いようです。
各部とも人数不足と照りつける太陽に苦しみながら,必死に研鑽を兼ねてきました。
頑張ってきてください。
2019年5月14日
2019年05月14日(火)
PTA総会
PTA総会が開催されました。
今年度も保護者の皆様,生徒のみなさんのご協力のもと,私ども職員はより一層情熱を持って教育活動にに邁進してまいる所存でございます。
何卒宜しくお願いいたします。
2019年5月10日
2019年05月10日(金)
第一回避難訓練 (地震・津波対策)
本日は地震を想定した避難訓練を行いました。
避難のお菓子で
(お)押さない
(か)駆けない
(し)ゃべらない
慌てずに集団行動!
キレイに並びました!
でも実際はなによりも命を優先してくださいね
大島消防隊員の方も来て下さり,緊張感が高まりました。
横断待ちをしている生徒の皆さん……。(あれ 江口先生?)
○消防隊員の松山様の講話
さすが消防隊員! 気合いの入った情熱的な自己紹介。
そして面白いお話と真剣なお話 「自分の命は自分で守ろう」
避難に必要なもの 避難経路のことなど
とても大切な話をして下さいました。
2019年4月17日
2019年04月17日(水)
生徒指導全体会
生徒指導全体会
本日は生徒指導全体会が行われました。
学校生活を明るく楽しいものにするための大切な会です
生徒は皆 真剣に聞いており,先生の質問にも自分なりの答えを出していました。
流石ですね(^0^)
皆で忘れ物ゼロの学校を作っていきましょう!
皆ならできる!
◎身だしなみについて
↑ 上の写真のようにビシッと着こなしたスーツや制服はきれいで,格好いいですよね ↑
オシャレ(自分本位)と区別して,場に応じた服装ができる。
服装を正して,お互い気持ちの良い挨拶ができるように
して参りましょう!